この記事は約5分4秒で読むことができます。
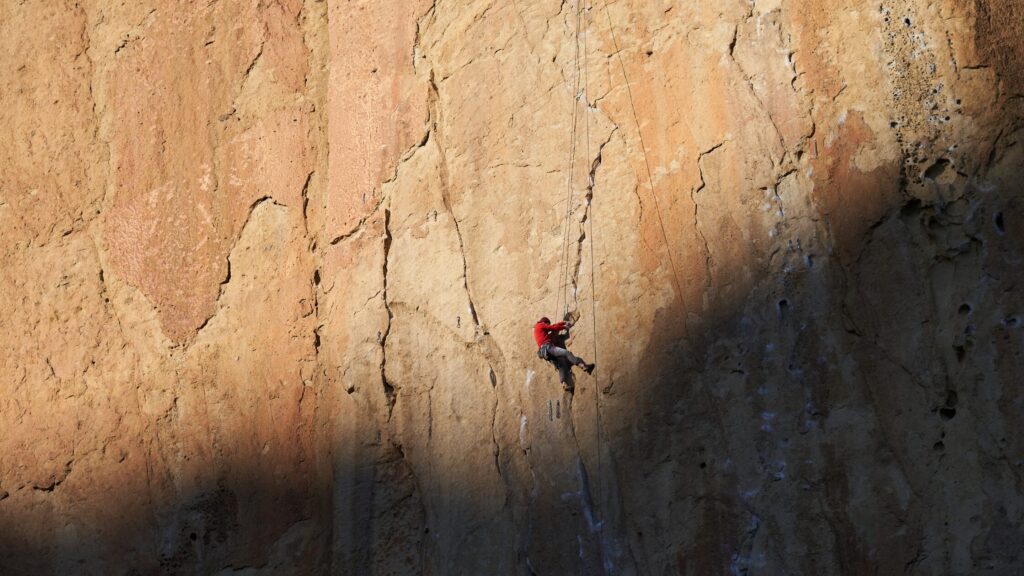
1. はじめに:「不退転の覚悟」は本当に美徳なのか?
「不退転の覚悟」という言葉は、ビジネスやスポーツ、政治の場面などでしばしば使われます。「後には引かない」「絶対にやり抜く」という気概が強調され、時に鼓舞や自己奮起の材料として好まれます。
しかし、本当にその覚悟は「後退できない」状況から生まれたのでしょうか?
実際には、「退くこともできるけれど、あえて前に進む」という余地と選択があるからこそ、人は腹をくくることができるのではないでしょうか。
この記事では、この逆説的な心理を、心理学の理論や実践知と交えながら紐解いていきます。
2. 覚悟と心理的安全性の関係
2.1 心理的安全性とは何か?
まずは「心理的安全性(Psychological Safety)」という概念から確認しておきましょう。
この用語は、ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授によって提唱されたもので、以下のように定義されています:
“a belief that one will not be punished or humiliated for speaking up with ideas, questions, concerns, or mistakes.”
(アイデアや質問、懸念、ミスを口にしても、罰せられたり辱められたりしないという信念)
出典:Edmondson, A. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly.
心理的安全性が高い環境では、人は「失敗しても受け入れられる」という前提があるため、リスクを取って挑戦することができます。つまり、「もし後退しても、許される」「失敗しても、まだ道がある」と思える状況こそが、人間にとっての安全な挑戦の土台なのです。
2.2 心理的安全性があるからこそ、前進できる
逆に、心理的安全性がない環境ではどうでしょうか?
「失敗したら終わり」「後退したら否定される」と思っている状況では、人は挑戦どころか思考停止や防衛反応に入ってしまいます。
この状態は、心理学でいう「学習性無力感(learned helplessness)」にも近い反応です。
自分の行動によって状況が改善しないと学習した人は、挑戦をやめ、受け身になります。
したがって、覚悟とは「追い込まれた結果」ではなく、「守られていると感じられるからこそ自分から踏み出す決意」と捉えた方が適切です。
3. 自己決定理論と覚悟の質
3.1 自己決定理論(SDT)とは?
エドワード・デシとリチャード・ライアンによって提唱された自己決定理論(Self-Determination Theory, SDT)は、人間の動機づけを3つの基本的欲求から説明しています:
- 自律性(自分の意思で選んでいる感覚)
- 有能感(うまくやれるという感覚)
- 関係性(他者とのつながりや受容)
この中でも「自律性」は、覚悟の本質に深く関係します。
3.2 「選べるからこそ、選ぶ」ことの価値
「不退転の覚悟」が意味を持つのは、それが自発的に選ばれたときです。
「逃げ道があるけれど、あえてそこに踏みとどまる」「やめてもいいが、進むことを選ぶ」という構図には、高い自律性が含まれます。
逆に、外からの強制や圧力によって「退けない」状況に追い込まれている場合、それは「覚悟」ではなく「従属」「服従」と言っても過言ではありません。
4. レジリエンスと「退転できる」強さ
4.1 レジリエンスとは?
心理学でいうレジリエンスとは、「困難やストレスから回復する力」、あるいは「しなやかに適応する力」です。これは、ポジティブ心理学の文脈でも重視されている概念です。
4.2 引くことができる人こそ、また進める
レジリエンスの高い人は、無理をして前進し続けるのではなく、状況を見極めて一時的に引く、休む、撤退することができます。
そしてエネルギーが回復したとき、再び前に進む柔軟性を持っています。
つまり、退転できる力=再起の力であり、それこそが長期的な「覚悟」を支える資源です。
5. 日本社会における「不退転」幻想
5.1 「背水の陣」という危うさ
日本のビジネス文化では、「背水の陣」や「逃げ道を断つ」という考え方が美化されがちです。しかし、これは短期的には集中力を高める効果があるものの、長期的にはバーンアウトやメンタル不調を引き起こしやすい危険な戦略です。
また、こうした言葉を用いる人が、自らの立場がどれだけ安全で守られているかを自覚せずに発言していることも少なくありません。
その結果、「覚悟なき者はついてくるな」といった排他的で非共感的な文化を生み出してしまいます。
5.2 本当に強い人は「逃げてもいい」と言える
真に成熟したリーダーや親、教育者は、「逃げるな」ではなく「逃げてもいい」と言える人です。
- 「休んでいい」
- 「今はやめてもいい」
- 「いつでも戻ってきていい」
という言葉は、相手に心理的安全性を与え、その人が自分のタイミングで再び前進することを支えます。
6. 終わりに:覚悟とは、自由の中で選ぶこと
「不退転の覚悟」とは、追い込まれた末の選択肢のなさではなく、あらゆる可能性を把握したうえで「進む」を自ら選ぶ姿勢です。
その覚悟は、以下のような条件のもとだからこそ育まれます:
- 心理的安全性という土壌
- 自律性という動機
- レジリエンスという柔軟性
それらを無視して、ただ「覚悟を決めろ」と言うのは、時に暴力的でさえあります。
だからこそ、私たちが「退転できる場所」を他者に、そして自分に許す社会を築くことが、結果として強さや持続性につながるのではないでしょうか。
個別無料説明会(オンライン)について

ライフコーチングを受けたい方はオンライン無料説明会へお申し込みください。

説明会は代表の刈谷(@Yosuke_Kariya)が担当します!お待ちしています!
コーチング有料体験について
実際にコーチングを体験してみたい方向けに、有料のコーチング体験も用意しております。ご興味のある方は以下をクリックください。
-

統合型パーソナルコーチング体験セッション|本気で人生を再設計したい方へ
この記事は約7分31秒で読むことができます。 目次 / Contents なぜ「体験」という場を設けているのか時間の数を超えた「経験の厚み」を統合する統合されている「4つの知性」本気で向き合うための「 …

